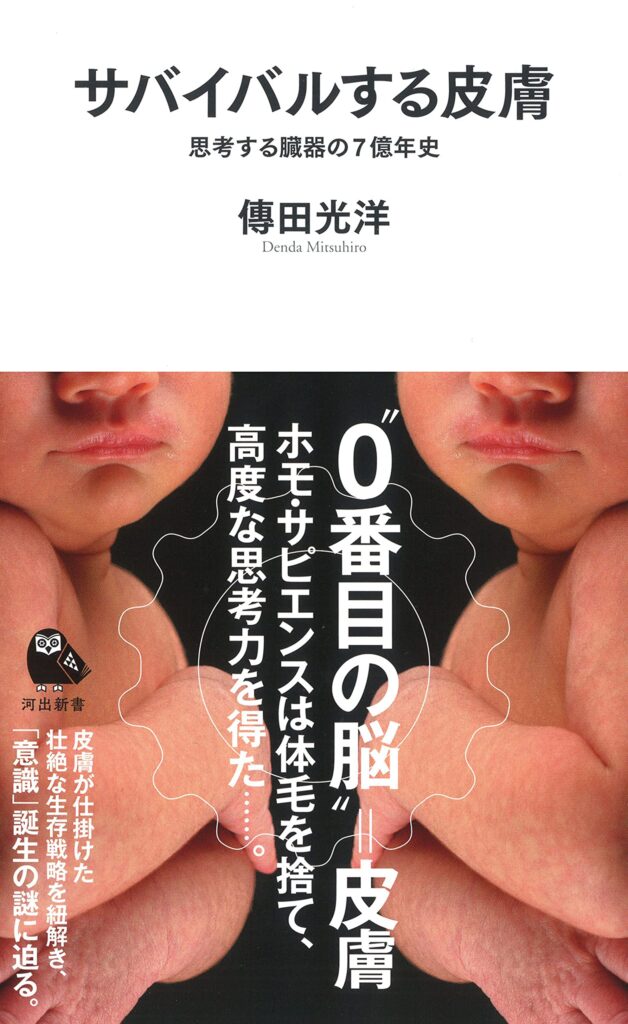進化過程から考える皮膚の脳の役割分化・・・様々な固定観念を超えて
現在では、脳がすべての判断を担っているような『脳絶対主義』が巷に溢れ、これこそが人類の証であるような論調に支配されている。確かに人類の脳は大きく、機能的にも他の動物に比べ処理能力が高い。
しかし、地道で精度の高い研究をされている傳田光洋氏の書籍を読んで、『脳絶対主義』という固定観念から離れてみると、その機能が発揮される基盤に、人類の皮膚判断機能の増大と高度化があったと考えられるのではないか?と感じた。
1.皮膚の判断と目や耳などの専門感覚器官の判断の違い
皮膚は、感覚機能だけでなく判断機能をもつ。それも、目や耳ななどの専門特化した判断器官に比べ、はるかに広範囲な外圧を受信して判断している。判断する機能部位は脳とほとんど同じ受容体で、それはケラチノサイトという皮膚層の中にある。
これらは現在では、単純な刺激応答試験から、特定のレセプターを遺伝子操作で壊した個体との対照試験まで、様々な実験が実施され明らかになってきている。
次に、皮膚が感取・判断できる外圧は、温度・圧力・気圧・可視光・広範囲の電磁波・味・匂い・磁気・・・と極めて多種の情報があり、『その判断も含めた情報』を脳に送る。
他方、脳には耳や目などの専門感覚器官から、皮膚より詳細な情報が届くが、これらの情報域は、皮膚が受信・判断したそれよりはるかに狭い。この2種類の情報を突合せ最終判断を行い行動に繋げる。
その際の、皮膚の受信・判断情報と専門感覚器官から脳へ至る情報の違いはなにか?
まず、皮膚からの情報は極めて多種で、一種当たりの受信範囲も、専門感覚器官に比べはるかに広い。しかし、解像度は、専門感覚器官に比べ、低い。そして、顕在意識には上りにくい。
他方、例えば目が受信できる電磁波の波長は、皮膚が受信できる波長のほんの一部でしかないことからわかるように、専門感覚器官の感受範囲は狭い。しかし、その狭い範囲の中で皮膚より高密度で解像度の高い情報を感受し脳に送っており、これは顕在意識と強く結びついている。
これは、単細胞時代からの感受・判断器官がまず基底にあり、その内、適応のためには何としても強化したい感受機能を担う専門感覚器官を、対象と受信領域を絞り精度をあげ作り上げたのだと思われる。
つまり、無意識に感じ取っている皮膚の感受・判断情報を脳の判断基盤として、その上に、目や耳などの、対象領域を絞った濃密な受信情報を塗り重ね、階層構造の中で判断しているのだと思われる。
また、人類の場合は、他の哺乳類に比べて、体毛が極めて少なく感覚・判断器官として皮膚が極めて広くなり、受信・判断できる情報量も大幅に増えた。
これは、先端機能を更に強化するために、根源である基盤機能の皮膚の受信・判断機能も更に強化しながら、全体として、より精度を上げて判断できるようにしたのではないか?
このような、膨大な情報を処理するために人類の脳は大きくなったと考えられる。
2.不食の人も、皮膚と脳の関係に似た存在構造がある
宇宙からの波動エネルギー(≒自然電磁波)を受信・利用している生命体は、単細胞から多細胞まで今でも存在しており、その根源にはソマチッドがあるのだと思う。
そして、人類の皮膚も多くの自然電磁波を受信している。ところで、現在不食の人は世界で5~6万人存在する。そこには、訓練によって不食に近い状態を作り出している人も含む。
それがなぜ可能か?それは、皮膚が自然電磁波を受信・利用しているからということが挙げられるが、それ以上に、大きな認識転換が必要になる。
それは、不食を実現している多くの人々に共通する感覚として、食べて得られるエネルギーは、そもそも必要なエネルギーの10%~30%程度で、残りの70%~90%は、それ以外からとっているというものだ。
そうであれば、10%~30%程度のエネルギーを皮膚やその他から受信・利用できれば不食は実現できることになる。これも、『栄養学絶対』という現代人の固定観念から『不食の人など信じられないという』誤った信念が生まれたことになる。
つまり、よくわかっていないことだらけの世界を知るためには、まずは、その現象に真摯に向き合い、現象が事実であれば、それを否定する観念のほうを疑ってみることで、固定観念を超えていく必要があるのだと思う。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2022/05/6311.html/trackback