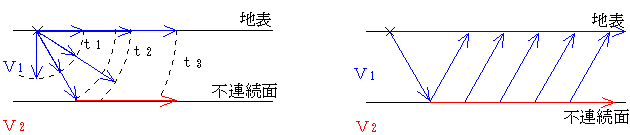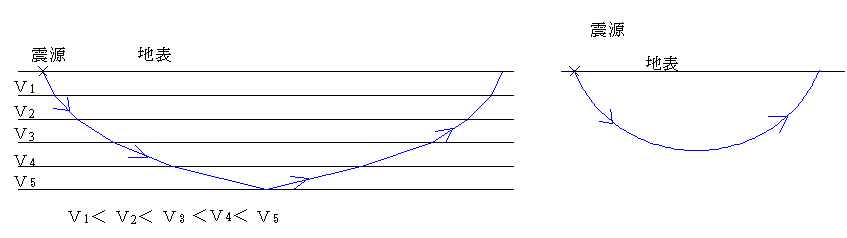【地球の内部 1】 地球の内部構造をどうやって推測したのか?
電磁波は地震を引き起こすのか?について、地電流や地磁気との関係などのマクロ的な視点と、電磁波の共振現象などのミクロな世界の視点で調査をしてきました。しかし、これら解明のためには、地球内部の構造や物性や大気圏を介した宇宙や太陽との関係についてのより詳細な把握が必要なことがわかりました。
そこで今回から、シリーズで【地球の内部】として、物質組成・温度・圧力・導電性などの物性について扱います。その後【地球と太陽】というシリーズで大気圏を含めた宇宙空間と太陽との関係の中で、電磁波・電子・素粒子はどのような関係にあるのかを扱いたいと思います。
どちらのテーマも、この5年くらいの間に、超高圧実験による高圧下の物性や人工衛星による太陽の観測、国際宇宙ステーションによる大気圏の状態把握など、細分化された領域で新しい成果が出始めたという状態です。これらを調査して、その全体像はどうなっているのかの推定を行っていきたいと思います。
今回は様々な断面で捉えられている地球内部をこのブログでは地球を構成する物質の割合、どのような層にどのような鉱物が存在するのか、さらに、地球内部の気圧と温度、力学性質を述べていきます。
まず初めに今回は地球の基本構造と、その考え方について述べていくことにします。

★★★地球の内部構造
まずは、地球内部の基本構造はどのように組成されていると考えられているか図で表します。
http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/chisitsu/kakougan/rock-magma.html

上記の絵は現在の地球の内部構造をあくまで推定したものでしかありません。
人類は未だ地球の2%しかない地殻すらも掘り抜くことが出来ておらず、内部まで掘って調べた訳ではありません。
では、どのような方法で地球内部の構造を考えたのでしょうか。その方法と歴史について紹介します。
★★★地球内部の推測方法
まず、地球内部の層を推測するためには「地震波」を使います。地震波とは地震が起こった時の揺れの種類であり、P波(Primary wave)とS波(Secondary wave)に分けられます。
~以下はこちらより引用~
①縦波:P波(Primary Wave)
・進行方向:波と同じ方向に振動
・伝搬速度:速い(地表附近で5~7km/秒)
・伝搬媒体:固体・液体・気体の全て②横波:S波(Secondary Wave)
・進行方向:波と直角方向に振動
・伝搬速度:遅い(地表附近で3~4km/秒)
・伝搬媒体:固体中のみ(液体・気体は伝わらない)
~引用終わり~
簡単な地震波の伝わり方アニメーションがこちらで見ることが出来ます。
http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle/flash/ps_wave.html
地球が単一の層が連続しているなら、ある地点で地震が起これば全ての範囲に平等に地震波が伝わるはずです。
しかし、地震が起こった時に伝わる地震波は平等には伝わりませんでした。そこで、地球は単一の層だけでは無いのでは無いかという考えが生まれました。
それが以下の図です。
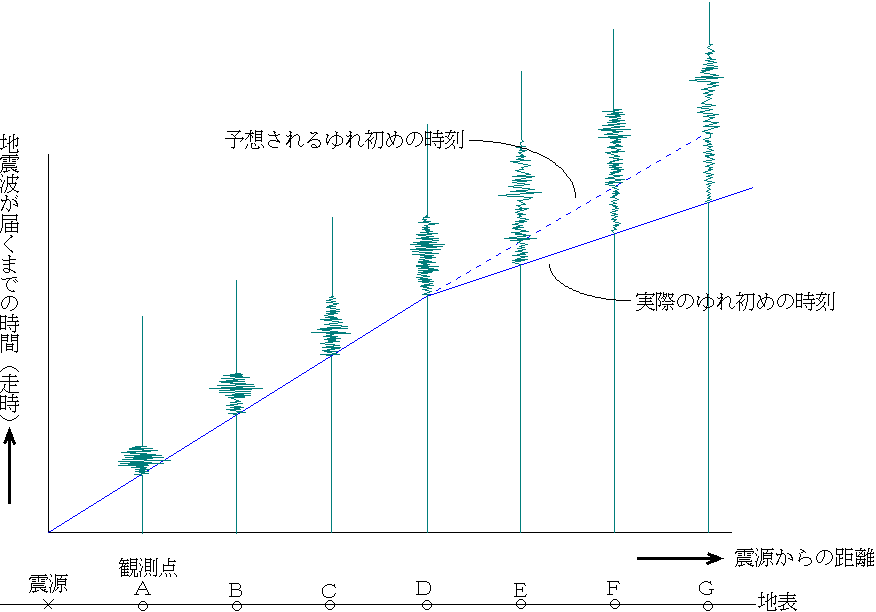
震源での揺れはある地点をもって伝わりが速かったのです。
それは以下のところで説明されています。
★地殻とマントルの間にあるモホロビチッチ不連続面
~以下「第二部-2- 地球の科学」より引用~
b.モホロビチッチの解釈
モホロビチッチは、地球内部は均質、あるいは深さとともに連続的に密度が増す(地震波速度が速くなる)のではなく、ある深さで不連続的に変化する(地震波速度が急に速くなる)のではないかと考えた。つまり下の図のように、ある深さで地震波の伝わる速さがV1からV2(V1<V2)に変化すると考えた。
震源から出た地震波はまず同じ速さV1で、つまり震源を中心として(断面で考えると)同心円上に四方八方に広がっていく。しかし、地震波の伝わる速さが急に変わる面(不連続面)に達すると、地震波はそれより深いところとはその境界面(不連続面)ではより速いV2という速さで伝わることができる。
そして、地震波はその境界のあらゆる所から、再び地表に向けて出てくる(図にはかいていないが本当はより深い向きにも出ている)。この地震波は再び遅いV1というさである。
地表で、どのような経路で伝わってきた地震波が最初に届くかを考える。震源からの距離が近いうちは、震源から地表をまっすぐに伝わってきた波(直接波)の方が速く届くのは明らかである(下図(1))。しかし、震源からの距離が大きくなると、下を回ってきた波(屈折波) の方が、距離的には遠回りだが、不連続面をより速い速さV2で伝わることができるので、時間的には近道になる。つまり、不連続面を回ってきた屈折波の方が 早く届くことになる(下図(3))。ちょうど、高速道路を利用するときに、あまり近い目的地だと高速道路を使う意味はないが、遠くに行くときはIC(イン ターチェンジ)まで行って、そこからまた目的地に向かうために距離的には遠くなっても、目的地には早く着くことができるのと同じことである。
そのちょうど境目、つまり直接波と屈折波が同時に到着する点がある(上図(2))。これが上の走時曲線のグラフでの観測点Dである。D点より震源に近い観測点では直接波が早く届き、D点より遠い観測点では屈折波が早く届くのである。こうして走時曲線が折れ曲がる。
モホロビチッチは、波の屈折の法則(スネルの法則)から不連続面までの深さを求めた。
補足説明:
地球内部を伝わる地震波:地球内部に行くほど上の重さがのしかかってきて、物質の密度は高くなり、また物質そのものもかたくなるので地震波が伝わる速さが速くなる。そこで、薄い層ごとにだんだんだん速くなるとすると(下左図)、境界面を通過するたびに下図のように屈折をして、最後にはより深い層へは入り込めずに、ある深さから再び地表に向かう波となる。
不連続面を除けば、地球内部ほど地震波の伝わる速さは連続的に速くなる。つまり、下左図の各層をもっともっと薄くしたことと同じである。そこで、地震波は下図のように地球の中心に向かってなめらかな凸の弧を描いて伝わることになる。
~引用終わり~
地震波の伝わるスピードが変わることからここで層が変わっているということがわかります。
モホロビチッチ不連続面はモホ面と呼ばれ、このモホ面を境として地殻とマントルが分かれていると推測されています。
地震波が伝わるスピードが変わる原因は次回以降にマントル等の力学的性質で述べるので、今回は割愛します。
★マントルと核の間にあるグーデンベルグ不連続面
次に、最初で載せた図においてマントルの下に核があるとされていますが、これについても地震波を使って測定されています。
マントルと核の境は地震学者グーデンベルグが発見し、これをグーデンベルグ不連続面と言います。
地震学者グーテンベルグ(1889年~1960年)はアメリカの地震学者で、地球の深いところにも不連続面があり、そこを境にして地震波の伝わる速さが急に遅くなることを発見しました(1926年)。
グーデンベルグの理論は以下となっています。
・103°~143°の地域にはP波は届かないことから、この地域をP波の影(シャドーゾーン)と言い、103°より遠くへはS波は届かない。
・このことから2.900㎞の深さの外核は液体であることがわかる。この面をグーテンベルグ不連続面と言う。
上記の考えにより、2,900kmの所でも層が変わる(不連続面)ことが推測され、それがマントルと核の境目である「グーデンベルグ不連続面」だということになります。
★核内部におけるレーマン不連続面
最後に、地球内部の基本構造図で、核には液体鉄の外核の中に固体鉄の内核があるとされています。
この核にも不連続面があると認識されたのは1936年で、地震学者のレーマンが発見しました。
レーマンはこれまで地震波であるP波もS波も届かないと考えられていたシャドーゾーンに地震波が微弱ながら届いていることを知ります。
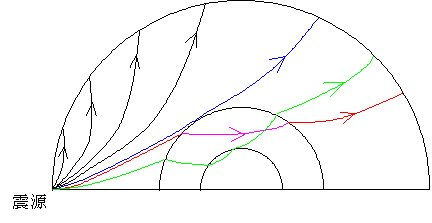
さらに、地球内部5,100kmでも急激に地震波が伝わる速度が変化していることから、核内部にも不連続面があると考えました。それから、外核と内核は液体と個体の間にはレーマン不連続面と呼ばれています。
以上が地球の基本的な構造となっています。次回からは、地球内部をさらに探索していきます。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2012/09/1194.html/trackback