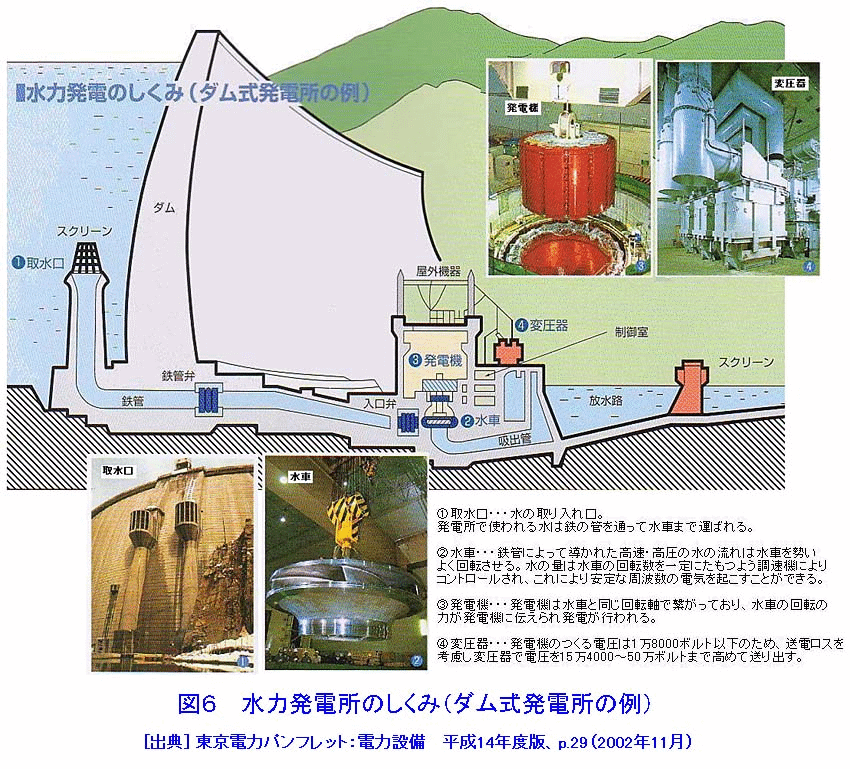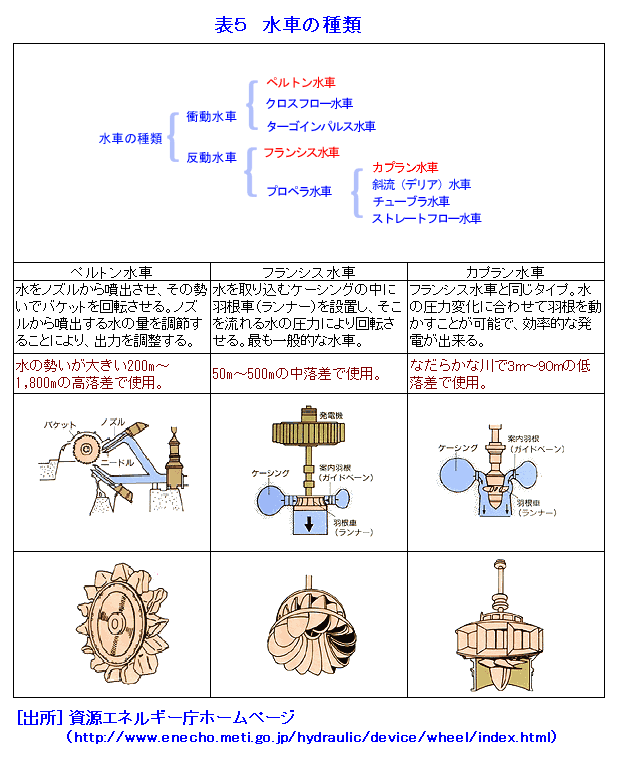『次代を担う、エネルギー・水資源』水生圏の可能性、水力エネルギーの活用 3.水力発電の黎明期

ビュフェが描いた三居沢発電所のスケッチ(仙台シニアカフェから引用させていただきました。)
前回は、人類が昔から水車を使って水力エネルギーを動力に転換し、実に多様な生産活動に利用してきたことを紹介しました。
今回は、現在の主流である電気エネルギーの利用へとどのように移行していったのかを明らかにしていきます。
↓応援をお願いします。
1.電気実用化の歴史
(以下、電気の歴史イラスト館 を中心に引用させていただきました。)
【古代の電気】
今から2500年前、ギリシャの哲学者タレスは、琥珀を摩擦した時の静電気による引力を発見しました。それ以前のエジプト時代には、金メッキや亜鉛メッキなどの装飾品が出土していますが、メッキ加工は電気を使わなければできないため、その時代のエジプト人は電気を理解していたかもしれません。
ちなみに琥珀のことをさすギリシヤの言葉(elecktra:エレクトラ)からエレクトロンという言葉がうまれました。
【電気の原理を追究する時代】
電気に関する発展のきっかけとなったのは、1752年、ベンジャミン・フランクリンの雷雨の中で凧を揚げる実験です。 凧糸を伝わってきた稲妻からの電荷を捉えた実験で、電気は遠い昔から観察されてはいましたが、この実験は稲妻が電気現象であることを証明した画期的な実験でした。
その後、ガルバニーの蛙の脚の実験で筋肉が電気によって痙攣するとの論文を読んだボルタは異なる金属間に発生する電気を発見し、1800年に電池を発明しました。
そして、1800年代前半に、オームの法則、電磁誘導の法則、電流の熱作用などの電気に関する原理が次々に明らかになりました。
【電気の実用化の時代】
電気の実用化の領域では、1800年代後半に、モールスが電信を、エジソンが電灯を発明しました。
また、回転運動と電流の相互変換が可能であることが分かり、発電機および電動機が発展していきました。
そして、1882年にエジソンが、ニューヨーク市で最初の発電所を作って街燈を点灯させ、一般需要家へ電気を供給する事業の基礎をつくりました。
そう、電気の実用化が始まったのはつい150年前、とその歴史はとても新しいのです。
エジソンの発電所は火力発電所でしたが、「存在の普遍性が高く、エネルギーを取り出すメカニズムも比較的簡単で、潜在エネルギーの水準も高く」、水車の原理をそのまま使って電流を発生させることのできる水力による発電が遥かに合理的です。
そうしてその後、水力による発電が広まっていくのです。
2.水力発電のしくみ
水力発電のしくみを、ATOMICA文中から紹介します。
水力発電は、水の力を利用して電気を生み出すもので、せき止めた河川の水を高い所から低い所まで導き、その流れ落ちる勢いにより水車を回して発電する。このときの発電量は、水の量が多いほど、また、流れ落ちる高さ(“落差”)が大きいほど増加する。
ポップアップ!
(1)取水口・・・発電所で発電に使われる水は、取水口と呼ばれる水の取り入れ口から鉄の管(水圧管(路))を通って水車まで運ばれる。取水口は貯水池の池底よりやや高いところにあり、土砂や魚、流水などが流れ込むのを防ぐため、丈夫なスクリーンがかけられている。
(2)水車・・・鉄管によって導かれた高速・高圧の水の流れは水車を勢いよく回転させる。水の量は水車の回転数を一定に保つよう調速機によりコントロールされ、安定した周波数の電気を起こすことができる。
ポップアップ!
(3)発電機・・・発電機は水車と同じ回転軸で繋がっており、水車の回転の力が発電機に伝えられ発電が行われる。水力発電所の出力は水量と落差(放水路の水面からダムの水面までの高さ)によってきまり、理論出力(kW)=9.8(重力加速度)×水量(m3/秒)×落差(m)の関係がある。
(4)変圧器・・・発電機のつくる電圧は1万8000ボルト以下のため、送電ロスを考慮して変圧器で電圧を15万4000~50万ボルトまで高めて送り出す。
このようにして水車が生み出す回転力を電気エネルギーに変換し、送電技術を発展させることで電気を実用化していったのです。
それでは、日本の水力発電の歴史を見てみましょう。
3.日本の水力発電の黎明期
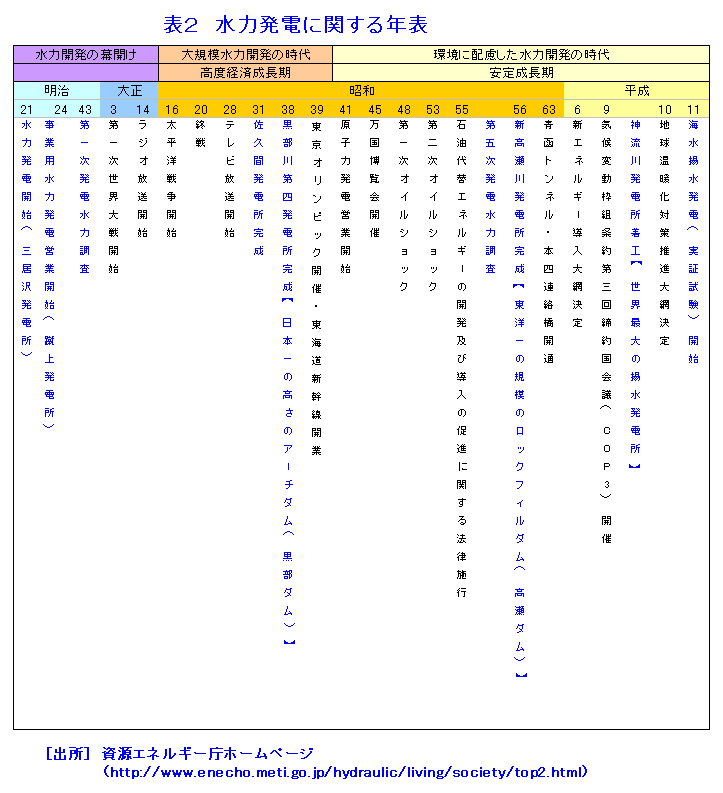
ポップアップ!
ATOMICAより借用させていただきました。
日本初の水力発電は、宮城の紡績工場の動力として使うために建設された三居沢(さんきょざわ)発電所(明治21年(1888年)で、その後も紡績工場や鉱山など製造工場に付設した自家発電所をつくってきました。
そして、明治24年(1891年)、日本最初の商用電力として琵琶湖疏水の水を利用した京都市営・蹴上発電所が開業しました。
日本の発電事業のエポックメーキングである蹴上発電所ができるまでのストーリーを見てみます。
概要は、ウィキペディア「琵琶湖疏水」より引用します。
疏水写真は京都市教育委員会HPから引用させていただきました。
禁門の変で市中の大半が焼け、明治維新と東京奠都に伴い京都市は人口が減少し産業も衰退したため、第3代京都府知事の北垣国道が灌漑、上水道、水運、水車の動力を目的とした琵琶湖疏水を計画。主任技術者として、大学を卒業したばかりの田邉朔郎を任じ設計監督にあたらせた。
第1疏水は1885年(明治18年)に着工し、1890年(明治23年)に大津市三保ヶ崎から鴨川合流点までと、蹴上から分岐する疏水分線が完成した。第1疏水(大津-鴨川合流点間)と疏水分線の建設には総額125万円の費用を要し、その財源には産業基立金、京都府、国費、市債や寄付金などのほか、市民に対しての目的税も充てられた。
また、水力発電は当初の計画には存在しなかったが、田邉らがアメリカで視察したアイデアを取り入れ、日本初の営業用水力発電所となる蹴上発電所を建設し、1891年(明治24年)に運転が開始された。この電力を用いて、1895年(明治28年)には京都・伏見間で日本初となる電気鉄道である京都電気鉄道(京電)の運転が始まった。
京都が、疏水造営、発電事業、電気鉄道などを進取の気性で最新の技術を導入してきたのも、実は東京奠都で没落寸前の危機感があったからだったのです。そして、それぞれに実現へと導いた優れたパイオニアがいたのです。
蹴上発電所の場合は田邉朔郎でした。
琵琶湖疎水の略図
ポップアップ!
京都市上下水道局疏水事務所HPの地図を加工させていただきました。
『京都を蘇らせた琵琶湖疏水~これからは水力発電の時代だ』より
京都府知事北垣が、琵琶湖の水を京都に引く「琵琶湖疏水」工事の実現に東奔西走していたころ、田邉朔郎は工部大学校(現・東京大学)の学生だった。卒業を間近に控えていたため、卒業論文にちょうど取り組んでいた。卒論のテーマは「琵琶湖疏水工事計画」だった。
当時の工部大学校の学長、大鳥圭介と北垣は、古くから知人であった。日本人だけで工事を完成させたかった北垣は、明治15年4月、大鳥に相談に行き、田邉朔郎を紹介される。北垣は、田邉朔郎という人物を知れば知るほど、その気骨に心打たれるのだった。
田邉にはこんなエピソードがある。田邉は卒論執筆のために、琵琶湖方面へ測量に通っていた。そこで測量道具である削岩機を右手中指に落とし、怪我を負う。田邉は家が貧しかったため、たいしたことはないとやせがまんして医者にかからないでいたが、じつは骨折していた。田邉は右手を吊ったまま、左手で精緻な製図を描き、左手で論文を書き上げた。大鳥はこのとき思ったのだ。「これだけの根性の持ち主なら、どんな難工事も、やってのけるはずだ」と。
北垣知事は当初、琵琶湖疏水工事の主任として、内務省の土木部長、南一郎平(安積疏水建設の主任技師)を招聘する予定でいた。だが、内務省は、一地方の土木工事に重要人物を貸すわけにはいかないと断った。
そこで明治16年、卒業と同時に京都府に採用されたばかりの田邉朔郎に、琵琶湖疏水工事の大事業を一任する。こうして、北垣の熱意と田邉の頭脳が両輪となって、明治18年に工事が開始された。
田邉はまた、新規開拓精神を持った人物でもあった。当初は水車動力を導入する予定だったが、アメリカで水力発電の機械があることを土木雑誌で知り、工事期間中に視察のため渡米する。
赴いた先はコロラド州アスペン。当時はアメリカでも、水力発電など荒唐無稽な技術だと物笑いのタネだった。けれども田邉は、これからは電気の時代だと確信する。水車動力は、広大な土地を必要とし、動力源である水車の近くにいなければ発生したエネルギーを利用できない。電気ならば、電線で遠くまでエネルギーを運べる。
田邉の進言で方針は変更される。発電機をアメリカから輸入し、明治24年、発電所が作られる。琵琶湖の水を利用した日本初の水力発電所、蹴上(けあげ)発電所である。
当初の蹴上発電所は、36mの有効落差を使ってペルトン水車(120馬力×2台)を回し、エジソン式直流発電機(80kW×2台)で発電するもので、その後増改築を重ね、現在も出力4500kWで電気を供給しています。
こうして、蹴上発電所を手始めにして、日本においても水力中心に発電事業が広がっていったのです。
次回は、明治政府から高度成長期までの歴史を追って、電力政策と発電方式の変遷(「水主火従」から「火主水従」)を見ていきます。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2010/11/788.html/trackback