新エネルギーってどうなの?
最近、新エネルギーって注目されてますよね? 😀
この間も、テレビ  で「小麦VSさとうきび バイオ燃料1Lでどこまで行けるか!?」という企画があり(ちなみに原付)、見ていました 😛
で「小麦VSさとうきび バイオ燃料1Lでどこまで行けるか!?」という企画があり(ちなみに原付)、見ていました 😛
そもそもバイオ燃料って何かしら?と思って見ていると、その内容にビックリ![]()
バイオ燃料といっても、そのうちの97%はガソリンで、3%が小麦とサトウキビを原料に作られたエタノールだったんです  何や~たったの3%なん?それって意味あるん?って感じですよね
何や~たったの3%なん?それって意味あるん?って感じですよね
バイオ燃料って?新エネルギーって?をちょっと詳しく考えてみる必要がありそうですね
まずは以前投稿されている、
『バイオマスってなに?1,2,3』
を参考に考えてみたいと思います

続きを知りたいと思った方は  ポチっとお願いします
ポチっとお願いします 
ちょっと読み進めてみると…
あらためてバイオマスってなに
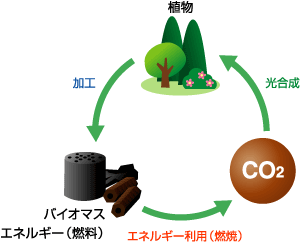
バイオマスは有機物であるため、燃焼させると二酸化炭素が排出される。しかしこれに含まれる炭素は、そのバイオマスが成長過程で光合成により大気中から吸収した二酸化炭素に由来する。そのため、バイオマスを使用しても全体として見れば大気中の二酸化炭素量を増加させていないと考えてよいとされています
1990年代以降、バイオマスは二酸化炭素削減(地球温暖化対策)、循環型社会の構築などの取り組みを通じて脚光を浴びています。そもそも高度成長期以前の日本では、落葉や糞尿を肥料として利用していたほか、里山から得られる薪炭をエネルギーとして利用するなどバイオマスを活用した社会であったと言えます。
ウィキペディア「バイオマス」により抜粋・編集
『バイオマスってなに?1』の↑の部分でちょっと「んん
 」と思いました。
」と思いました。
「バイオマスは有機物であるため、燃焼させると二酸化炭素が排出される。しかしこれに含まれる炭素は、そのバイオマスが成長過程で光合成により大気中から吸収した二酸化炭素に由来する。そのため、バイオマスを使用しても全体として見れば大気中の二酸化炭素量を増加させていないと考えてよいとされています」
の部分ですが、一見、理論上では「なるほど!」ですが、現実で考えたら…おかしくないですか
この理論でいけば、
今現在生えている木を切って、それが廃材になりバイオマスとして活用された→つまりエネルギーとして燃焼させてCO2を排出した→でもそのCO2は、その昔の木が成長する過程で光合成の際使用したCO2として換算すると、プラマイ0なのでOK
ってことですが、実際、木が使用したCO2は、その昔成長する段階に空気中にあったCO2なんだから、燃やした時点で考えれば、ただ単に燃焼して空気中にCO2が放出された→CO2が増えた ことになりますよね
燃焼させた時点でCO2をプラマイ0にしようと思ったら、その時点で放出分と同じだけのCO2を吸ってくれる植物を育てるなどしないと、そうは言い切れないと思います。
う~ん…しかしそれって可能なのか??
だいたい、植物ってどれくらいの量のCO2を成長時に吸収してくれるんでしょう?
と思ってたら、 こんなデータがあったので紹介します
図:身近なCO2排出と森林(スギ)のCO2吸収量
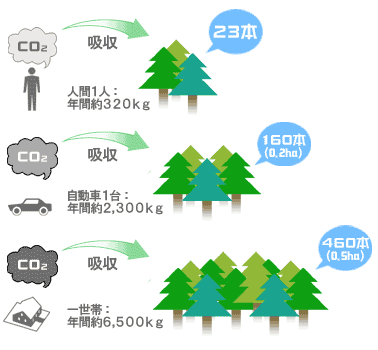
参照:環境いばらき
わ~8)
このデータを見る限りでは、人が普通に生活していく中で出るCO2を植物が吸収しきること自体が、もう無理そうだな…と思ったのですが…
これプラス、バイオマスで出るCO2を吸収するなんてできるんでしょうか
う~ん…やっぱりバイオマスには可能性がない気がします:cry:
これは、他の新エネルギーも調べる必要がありそうですね
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2007/06/156.html/trackback
コメント5件
仙台のくまさんです | 2007.08.26 3:55
はじめまして!仙台のくまさんと申します。
循環型社会の実現に関して、私のきずいた点を書き込ませていただきます。
循環型社会の実現の最大の条件は、成長経済から循環経済へ大転換が最大の必要条件のようですよ?
以下の事を検討され循環経済を目指すならば理想的な循環型社会が形成されてゆくでしょうね?このまま成長経済を目指せばいづれ国民は鉄砲を持ち戦わなければならないようになると思います。
。。。。。。。。。。。
地獄の釜が開くのかもしれません>>。。。。企業の利益一辺倒の判断がされていった場合には、地獄の釜は開かれるでしょうね?
各国の指導者たちがそれぞれの国の循環経済を進め、世界経済の循環経済へ転換する目標を立て、そのための為替操作を押し進めるならば、地獄の釜は、開かなくとも済むのでしょうけれどね?
早急に検討を!
戦争といゆものは、歴史上工業界の平均賃金と農業界の平均賃金の差がつき過ぎることからおきるようですよ?
戦争によつて食糧の重要さが出てきて、工業界の平均賃金と農業界の平均賃金が圧縮され、是正され、また年数が経つと工業界と農業界の平均賃金が差がつき戦争へと、何十年周期に戦争が起きるようになってるようです。
戦争を回避するためには人為的に工業界の平均賃金と農業界の平均賃金を近づけることです〔失業者0になるところまで)。
今、アメリカでは低所得層の住宅ローンが焦げ付き始まりましたね、これを回避するためには、アメリカの食糧の価値観をアメリカの家計費の割合で上げてゆくことです〔失業者0になるまで)。そうすれば、アメリカといゆ国は落ち着いてくると思いますがね。
潰れてゆくアメリカの真似事に集中しておるこの国〔日本)の国民性はどうなっておるのでしょうか?ましてや、この国は自給率が非常に低いです。この先のこの国の行く末の危険性を感じます。
財政問題にしろ、医療問題にしろ、年金問題にしろ、教育問題にしろ、治安問題にしろ、
すべては、インフレか、ハイパーインフレで食糧の価値観を家計費の割合で上げて行かなければ解決はしないようですね?…….
y.suzuki | 2007.08.26 22:40
仙台のくまさん、始めまして。これからもどうぞよろしくお願いします。
戦争問題も経済問題も、おっしゃるとおり、市場経済原理が根本にあるのだと思います。この市場原理は、幻想価値を上乗せすることで成立しています。それは政策上はGDP信仰となって表れます。つまり、先進諸国の指導者たちは、既に、市場原理支配者の奴隷と化しています。
一方、生活必需品(農産品)は、ほぼ実態価値のままで、価格格差は広がるばかりです。格差解消も必要かと思いますが、更にいえば、これからの社会にとって必要な価値とは何かを組みなおす意識が前提になるかと思っています。これもまだ明確に言葉にはならないけれども、みなの期待のひとつではないでしょうか?
詳しくは、trend review
http://www.trend-review.net/blog/
という政治経済系のブログがお勧めです。
ふれあい農園 | 2008.01.12 20:38
ミミズコンポスト
kibino | 2010.04.04 12:43
コメントを入力してくださ従来の経済の考え方は「資源発掘→加工生産→消費→廃棄」だった。
すると、「資源枯渇」「競争による倒産失業」「環境汚染」等の問題が起きる。
その解決策として考えたのが上記の図(下記blog内)である。産業を「衣食住×衣食住」で9つに分けた。それぞれの中でサービスが回転する。
・リサイクルするので資源枯渇や環境汚染が軽減する。
・バランスよく配分されて倒産や失業が軽減する。
ここには「生産と消費」というお馴染みの言葉でなく、「送填と受填」という新しい言葉を用いる。
http://blogs.yahoo.co.jp/k_kibino/61176047.html
い

はじめまして!仙台のくまさんと申します。
循環型社会の実現に関して、私のきずいた点を書き込ませていただきます。
循環型社会の実現の最大の条件は、成長経済から循環経済へ大転換が最大の必要条件のようですよ?
以下の事を検討され循環経済を目指すならば理想的な循環型社会が形成されてゆくでしょうね?このまま成長経済を目指せばいづれ国民は鉄砲を持ち戦わなければならないようになると思います。
。。。。。。。。。。。
地獄の釜が開くのかもしれません>>。。。。企業の利益一辺倒の判断がされていった場合には、地獄の釜は開かれるでしょうね?
各国の指導者たちがそれぞれの国の循環経済を進め、世界経済の循環経済へ転換する目標を立て、そのための為替操作を押し進めるならば、地獄の釜は、開かなくとも済むのでしょうけれどね?
早急に検討を!
戦争といゆものは、歴史上工業界の平均賃金と農業界の平均賃金の差がつき過ぎることからおきるようですよ?
戦争によつて食糧の重要さが出てきて、工業界の平均賃金と農業界の平均賃金が圧縮され、是正され、また年数が経つと工業界と農業界の平均賃金が差がつき戦争へと、何十年周期に戦争が起きるようになってるようです。
戦争を回避するためには人為的に工業界の平均賃金と農業界の平均賃金を近づけることです〔失業者0になるところまで)。
今、アメリカでは低所得層の住宅ローンが焦げ付き始まりましたね、これを回避するためには、アメリカの食糧の価値観をアメリカの家計費の割合で上げてゆくことです〔失業者0になるまで)。そうすれば、アメリカといゆ国は落ち着いてくると思いますがね。
潰れてゆくアメリカの真似事に集中しておるこの国〔日本)の国民性はどうなっておるのでしょうか?ましてや、この国は自給率が非常に低いです。この先のこの国の行く末の危険性を感じます。
財政問題にしろ、医療問題にしろ、年金問題にしろ、教育問題にしろ、治安問題にしろ、
すべては、インフレか、ハイパーインフレで食糧の価値観を家計費の割合で上げて行かなければ解決はしないようですね?…….