みなさんこんにちは 
今回は『太陽エネルギーシリーズ」』……を改め、
『素人が創る科学の世界【光子】シリーズ』をはじめます! 

最終的には、「電磁波とは何か?」という問題から「人体や地球への影響は?」を解明していくことが目的ですが、光も電磁波であり、「電磁波ってなに?」は「光ってなに?」とも置き換えられます。
ということで、この【光子】グループでは「光とは何ぞや?」をテーマにして、しばらく追求してみたいと思います 

 [1]
[1]
画像はこちら [2]からお借りしました  ありがとうございます
ありがとうございます 
前回の記事
(4)次代を照らす太陽エネルギー4~太陽エネルギーはどのように地球に到達しているのか~ [3]では
「電磁波が宇宙空間をどのように伝わるのか?」
「宇宙空間には媒質が存在するのか、しないのか?」
というテーマを扱い、
「宇宙空間には素粒子と呼ばれる超微細な物質が多く存在しており、電磁波を伝える媒質も存在しているのではないか?」
という仮説をたてました 
なにやらこれから数回にわたって、とても小さな物質の話を扱っていくことになりそう 
 なので、今回と次回では(電磁波を伝える媒質の存在やそのふるまいに迫る前段階として)素粒子のような小さな物質のふるまいを考える上で重要な「量子論」について探っていきたいと思います
なので、今回と次回では(電磁波を伝える媒質の存在やそのふるまいに迫る前段階として)素粒子のような小さな物質のふるまいを考える上で重要な「量子論」について探っていきたいと思います 
いつものお願いします 😀
☆☆☆そもそも量子論とは?
量子論というのは原子や分子、電子の様な量子スケールの世界で起こる出来事を記述するための物理体系です。
ニュートン力学などの古典力学では記述できないのか?と思うかもしれませんが、古典力学が量子スケールでの現象をうまく説明できない事は実験などで判っています。 量子スケールの世界では古典力学は使えないのです。
というのも、古典力学ではあらゆる物体について初期条件が測定できれば、その後の運動(位置と運動量)を完全に記述できるとされています。しかし、実際には原子や分子、電子、素粒子などの非常に小さなスケールの現象を扱う場合、粒子の位置と運動量は同時に両方を正確に測定することができないのです。(これに関しては次回扱うことにします。)
一方で、(前回の記事でも少し扱いましたが)光は「波」と「粒子」の二重性をもつことが知られています。そして、この「波」と「粒子」の二重性は光だけが持っているものではなく、実は、素粒子や電子、分子や原子など、量子スケールの物質はみんなが持っているんです 
今回は、この面白い性質が観察される実験を紹介しながら、量子論の不思議な世界を勉強していきましょう 
☆☆☆二重スリット実験
☆☆実験概要
 [4]
[4]
以下、画像はこちら [5]からお借りしました 
上の図を見てください。
電子銃の前にボードが置かれ、そのボードには「2つのスリット(隙間)AB」が開けられています。
そして、そのボードの奥にはスクリーンが配置されています。そのスクリーンはカメラのフィルムのように感光する性質を持っており、電子が当たるとその場所に白い跡を残します。つまり、スクリーンには、電子が当たった場所が映し出されるということです。
以上が、二重スリット実験の概要です。
概要がつかめたところで、いざ実験に進みましょう 
☆☆実験A ~一度に大量の電子を発射~
電子銃から大量の電子を発射します。
すると…なんということでしょう!下図のような模様がスクリーン上に現れました 
実はこれ、「干渉縞」とよばれる模様なんです ![]()
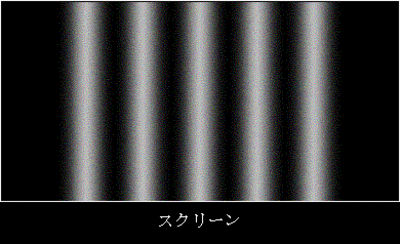 [6]
[6]
では、なぜこのような実験結果(干渉縞)が現れたのでしょうか? 
この実験結果、電子が「波」のふるまいをしていると解釈するとうまく説明できます 

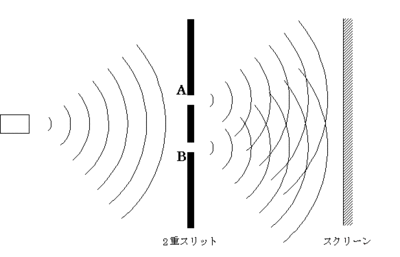 [7]
[7]
まず、電子銃から電子の「波」が飛んでいき、ボードに達します。
ボードには「2つのスリット」があるので、波は「スリットAを通っていく波」と「スリットBを通っていく波」の2つに分かれます。すると、スクリーン上にはその2つの波が重なり合ったものが見えるはずですよね?
つまり、2つの波の「山と山」「谷と谷」が重なっているところは、お互いに強め合って明るくなり、逆に、波の「山と谷」が重なっているところは、打ち消しあって波が消えてしまいその場所は暗くなってしまいます。
したがって、干渉縞が出現するのです。
実験Aの結果からは電子は「波」の性質をもつということが言えそうです。
☆☆実験B ~一粒の電子を発射~
次に、電子銃の出力を弱めて一粒の電子のみを発射します。
すると、スクリーン上にはポツンと小さな点が出現しました。
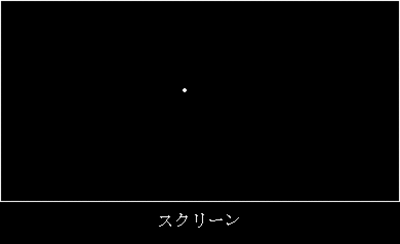 [8]
[8]
発射された一粒の電子は、スリットAかスリットBを通り抜けてスクリーンに到達します。
その一粒が当たった場所がスクリーン上にひとつの点として現れることはなんの不思議もありませんよね~ ![]()
![]()
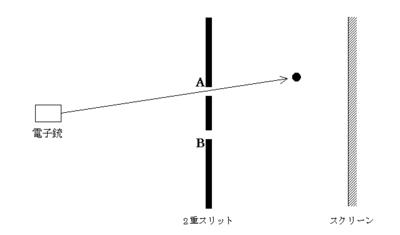 [9]
[9]
ここで確認のため追加実験として、スリットAとスリットBに電子を感知するセンサーを設置してもう一度実験Bをやってみましょう!
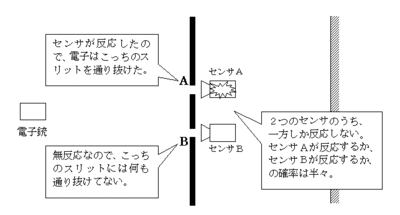 [10]
[10]
結果は
どちらかのセンサーしか反応せず、「一方のスリットを通り抜けたならば、もう一方のスリットは通り抜けていない」ということになりました!
やはり、
実験Bの結果からは電子は「粒」の性質をもつことが言えそうです。
ん??ちょっと待って!
実験Aの結果は「電子は波の性質をもつ」なのに、実験Bの結果は「電子は粒の性質をもつ」となってしまいました…。
一体どっちが正しいのでしょうか?
次の実験Cはもっと不思議です!
☆☆実験C ~大量の電子を一粒ずつ発射~
では次に、電子銃から「電子1個」の発射を何度も繰り返したらどうなるのでしょうか?
つまり、実験Bを何度も繰り返すわけです。
結論から言うと…なんと!実験Aの結果と同じ「干渉縞」がだんだんと出現してくるのです!
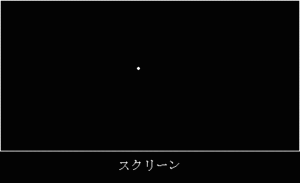 [11]
[11]
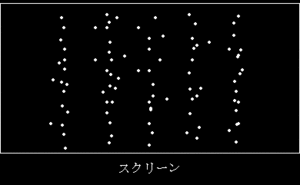 [12]
[12]
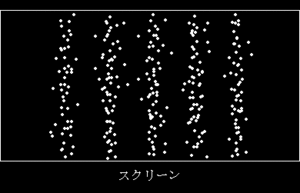 [13]
[13]
一体どういうことなのでしょう?
電子は粒としてスクリーンに現れているのに、その動き方は波になっている…?
なぜこんなことがおきたのでしょうか?
実験Cから得られた結果を一言で言うと
「電子1個がスクリーン上のどこで観測されるか?」という確率の分布が、干渉縞(波)の形になっている」ということです。
ではそもそもこの干渉縞とはどこからくるものなのでしょうか?
実験Aでも述べましたが干渉縞とは「スリットAを通り抜けたナニか」と「スリットBを通り抜けたナニか」が重なりあって現れる模様です。
当然スリットBを塞いで実験Cをやると干渉縞は発生しません!つまり、干渉縞の発生には2つのスリットが必要なのです!
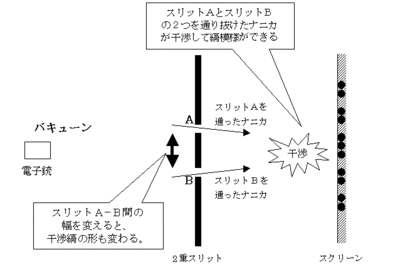 [14]
[14]
しかし!
ここで思い返してほしいのは、実験Cは電子を一個ずつ発射しており、その場合にはどちらかのスリットにしか電子は通っていないということが実験B(追加実験)からいえます。
ということは?スリットAを通り抜けた電子にとって、スリットBの存在はまったく関係なく、スリットAだけで実験したときと同じになるはず
ですよね?しかし、現実にはスリットAとスリットBによって決定される干渉縞が出現するのです 
これはもはや手に負えませんね  日常のアイデアでは上手く説明できなさそう…
日常のアイデアでは上手く説明できなさそう…
というわけで、このよくわからない実験結果を説明するための様々な解釈論が生まれたのです!
今回は長くなったので、それらの紹介はまた次回にします ![]()
ここまで読んでくださったみなさん、ありがとうございました 
(今回の記事はこちら [5]のブログを参考にさせていただきました 8) 8) )