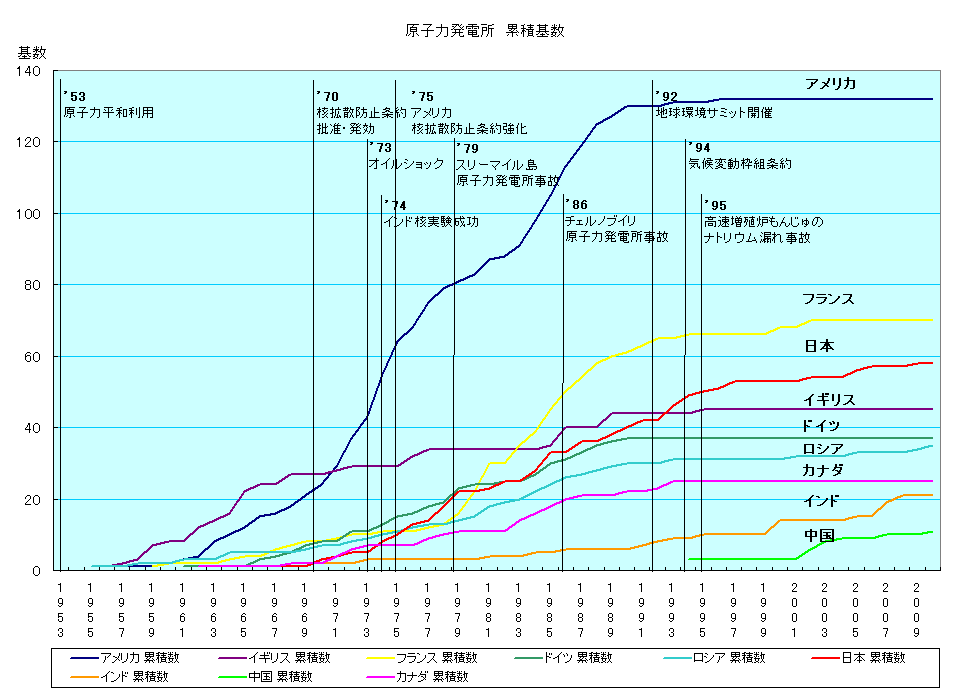1995年12月に起きたナトリウム漏出火災 事故以来、運転停止している高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)が、14年と5カ月ぶりに運転を再開した。経済産業省原子力安全・保安院の事前の立ち入り検査を経て、5月6日午前10時36分、日本原子力研究開発機構が原子炉を起動した。燃やした以上の燃料を生み出すことから、エネルギー資源の有効活用に大きく貢献するとして、「夢の原子炉」と期待されながら、事故で研究開発は頓挫。虚偽報告や現場撮影ビデオの隠蔽などで、国民の不信を増幅し、一時は廃炉の瀬戸際に立たされたこともあった。
当時の組織は解体され、2005年から2年か けて、ナトリウム漏れ対策の改造工事も実施、「もんじゅ」の安全性は大幅に強化されたという。『時事ドットコム』 [1]
『もんじゅ』の運転再開。推進派からは、いろいろな再開理由が出されています。しかし『何か、不透明な動きを感じてすっきりしない』というのが一般人の感覚だと思います。また、地元民を支援する反対派の理由も、国家としてエネルギー問題をどうする?や、壊されていく地元の共同体社会をどうする?といったという本質問題は脇においたままで、これも本質をぼやかしていくように見えます。
そして、研究開発着手開始から9000億円も投資して、いまだに数多くの問題を残したまです。それは、もんじゅ自体の技術的問題だけではありません。この、高速増殖炉の開発の前提となる、バックエンドと呼ばれる廃棄物の処理システムそのものが、さまざまな意味で実現可能な課題なのかどうか?という問題に行き着きます。
それゆえに、このような問題に触れることなく、反対か賛成かという二元論でしか議論できない現状が、今もっとも大きな問題なのだと思います。ここを何とかするために、日本における原子力推進体制の問題発掘を行い、今後のエネルギー開発体制に必要な条件を考えてみたいと思います。
まず今回は、概観まで。
☆☆☆世界の原子力開発の状況
『次代を担う、エネルギー・資源』トリウム原子力発電6-1/2 ~原子力発電を巡る世界の動き【先進国編】 [2]
『次代を担う、エネルギー・資源』トリウム原子力発電6-2/2 ~原子力発電を巡る世界の動き【発展途上国編】 [3]
2回に渡って、原子力発電を巡る世界の動きを見てきました。これらを年次別にもう少し詳しく見ていくと、大きな流れが見えてきます。
1990年前後から、市民運動の高まりとともに衰退して行く先進国の原子力開発と、それ以降、先進国からの技術供与で開発が進む中国という流れと、その中間にある自主開発のインドという3つの流れがあります。ところが、日本だけは先進国の中でも開発スピードは落ちたものの、増加傾向は変わっていません。
☆日本を除く先進国の原子力発電所建設は頭打ち
日本を除く先進国では、新規原子力発電所の建設は、安全性に対する市民運動の高まり等で、1990年前後から頭打ちになっています。1976年のスリーマイル島原子力発所電事故(アメリカ)1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故(旧ソ連)を契機に、原発の安全性への信頼はなくなり、緑の党など政党により反原発の世論が政策決定に影響を及ぼすようになったからです。
☆核保有国を震撼させたインドと核拡散防止条約
インドは後発で、民生利用として自主開発路線をとっていました。しかし、1974年核実験に成功し、核保有国を震撼させました。つまり、目的は民生利用でも、原子力発電は発電と同時に核爆弾の材料を生成し、簡単に軍事利用が出来るということが実証されたからです。
そして、先進国の核保有優位性が損なわれた結果、アメリカを中心にして核拡散条防止条約の強化に入り、民生利用の原子力開発もさまざまな制限を受けることになります。日本も例外ではありません。日本ではプルトニウムに直接関係するバックエンド技術開発にブレーキがかかりました。
この頃から、原子力の民生利用と軍事利用は切り離せないというのが世界的常識になりました。ただし、日本だけはこの常識からずれてしまっており、民生利用は核の軍事利用と関係無いという幻想を抱いたままです。このことは外交場面で大きな問題になる可能性を秘めています。
☆☆☆金貸しが支配する市場戦略と原子力開発
最近では、フランスのサルコジ大統領が途上国に向けて原子力発電技術の売り込みを積極的に行うという発言をしています。この流れの源流はどの辺りにあるのでしょうか?
☆途上国では、先進国が頭打ちになった頃に原子力開発が開始された
1990年前後に、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・カナダ等の先進国で原子力発電所が頭打ちになったあと、中国の原子力発電が始まります。先進国内で需要が減った分、国外輸出で原子力産業の需要をまかなってきたということだと思います。その中心はフランスで、カナダがそれに続きます。ただし、2000年以降の中国は、先進国の技術供与を受けながら自主建設を行っています。
☆地球温暖化問題の中で、原子力が救世主に?
1992年には、地球温暖化問題を世界的に知らしめる場となった地球環境サミットが開催されました。これを境に、温暖化問題の実態解明より、危機を煽る報道とそれに対応する政策決定の議論が主になりました。そして、いつの間にか直接CO2を出さないという理由だけで、原子力がこの問題解決の救世主のように言われるようになりました。
そして現在では、停滞し続けていた原子力市場の巻き返しが始まり、『原発500基争奪戦 東芝・三菱重・日立が増産や合弁で受注強化』 [5]
のように、原子力発電が世界的な建設ラッシュを迎える模様です。これらの現象が示す内容は、排出権取引と同様、金貸しが支配する市場戦略の中に原子力開発があるということだと思います。
以上が大きく捉えた世界の動きです。では日本ではどうなっているのでしょうか?
☆☆☆日本での原子力発電所数は、一貫して増加している
日本の原子力開発も、現在では他の先進国同様に国民的コンセンサスが得られているわけではありません。それでも開発が進められていることになります。
☆次々に代わる原子力開発を推進する理由
原子力開発の推進理由は次から次へと変わっています。初期は、夢のエネルギーとして、石油に比べて効率的優位性が謡われていました。次に、効率的優位性は無いことが明らかになり、石油に代わり増加するエネルギー消費をまかなえるのは原子力だけという理由に変更されました。そして現在、温暖化を防ぐ救世主としての原子力という理由が主流になってきました。
このように、首尾一貫した理由は無いにも拘わらず、長年の間、計画的に原子力発電所が建設されてきました。
その理由は、
☆官僚機構・電力会社を中心とした、強固な意思決定集団の自己増殖
日本の原子力開発推進体制は、官僚機構・電力会社を中心とした、政府からおおむね独立して意思決定を行える集団が、その制度を自ら強化し推進できる、自己増殖体制を確立したからです。アメリカの軍産複合体と酷似した体制的特長をもち、サブガバメントモデルともいわれています。官僚の暴走という現代的問題に重なります。
具体的には、官僚機構・電力会社の自己増殖集団は、社会的に要請される理由を超えたところで、原子力開発そのものに価値があるという共認と、世論の圧力をうけず強力に事業推進できる体制を持ち合わせてる、ということです。
この結果、世論に対して強行に政策実現できる体制が、推進派と反対派の対立を作り出し、とその狭間で地域住民の存在基盤である共同体をことごとく破壊してきたというのが日本の原子力開発の大きな流れです。
このように、国家規模で政策決定していく必要のある事業の推進体制は、エネルギー開発に限らず、官僚を中心とする利益集団の権益実現に収束してしまうという大きな問題を孕みます。ここを組み替えない限り、まっとうなエネルギー開発は実現できないといっても過言ではありません。
次回以降これらについてもう少し詳しく見ていきます。
参考:『原子力の社会史』吉岡斉 朝日選書