今回から、『次代を担う、エネルギー・資源』プロローグ [1]に引き続き、まず「状況編」として現在、世界や日本におけるエネルギーの使用状況がどうなっているのかについておさえていきたいと思います。まずは、下記グラフをご覧ください。
1.世界のエネルギー消費の現状
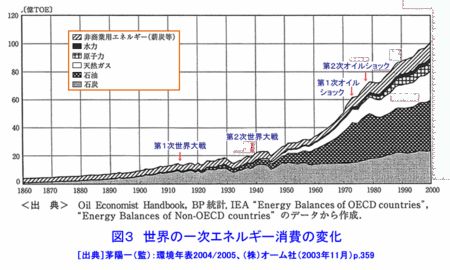 [2]
[2]
「人類とエネルギーとのかかわり」 [3]よりお借りしました
産業革命以降、特に20世紀前半までは主要なエネルギーは石炭が牽引し、そして1950年からは石油の消費が急拡大、そして1970年代以降に2度のオイルショックを経て、天然ガスと原子力が急拡大してきています。
そして、長期で見れば人類は石油エネルギー利用が可能になったことで「工業生産社会=多大なエネルギー消費型社会」へと転換してきたことがわかります。
では、この全体状況を踏まえて、次にこの40年に絞って世界と日本のエネルギー消費状況の詳細を見ていきたいと思います。
では、その前に応援よろしくお願いします。
次に日本でのエネルギー消費の推移を見てみましょう。
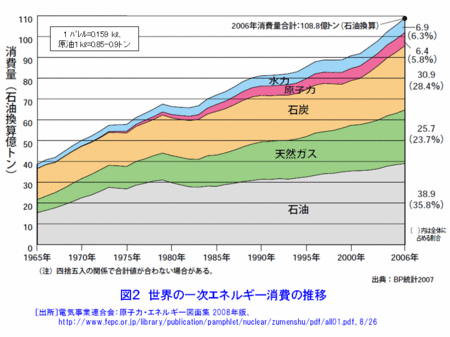 [4]
[4]
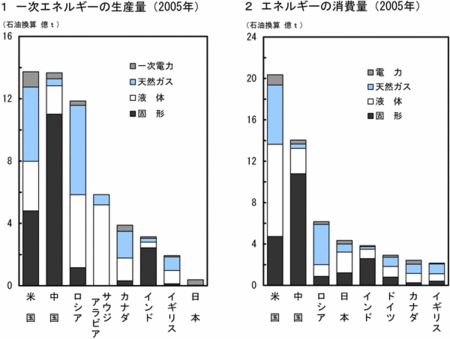 [5]
[5]
世界の石油資源 [6]および統計局「世界のエネルギー」 [7]よりお借りしました
現在、世界全体で「石油」「天然ガス」「石炭」の化石エネルギーの合計で87.9%を占めていることに驚かされます。脱石油エネルギーの代表である原子力なども5.8%に過ぎません。やはり、現時点では石油を代表とする化石エネルギーに頼らざるを得ない現状が明らかになります。
また、各国別の消費量では、先進国が世界の大半のエネルギーを消費しています(ただし中国の存在感は際立っていますが)。
そして、日本は、世界第4位のエネルギー消費社会でありながら、96%を輸入に頼り、エネルギー自給率は4%にしか過ぎません。
2.日本のエネルギー消費の現状
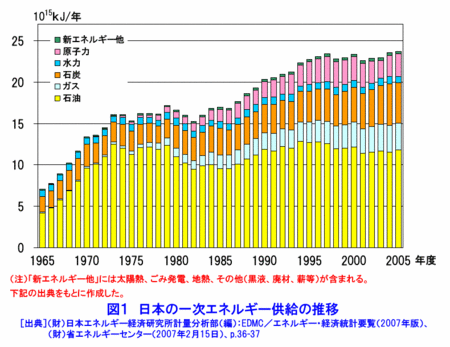 [8]
[8]
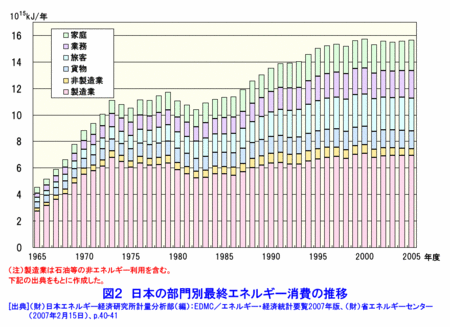 [9]
[9]
「日本のエネルギー供給とその推移」 [10]および「日本の最終エネルギー消費構成と推移」 [11]よりお借りしました
日本の場合は、世界と同様に1950年代からは石油の比率が急上昇し高度経済成長を支えてきたのですが、2度のオイルショックを経て石油消費量はほぼ横ばいをだどっています(‘70年以降は天然ガスと原子力の比率が上昇)。
そして、部門別エネルギー消費で注目すべきは、‘70年に貧困が消滅以降(主にはすべての家庭への耐久消費財の普及による高度経済成長の終焉)では、産業部門、つまりは工業生産はほぼ横ばいに転じているということです。
<参考>
『生産様式の転換と社会構造の変遷』 [12]より引用
共同関係の社会 武力支配 資本主義 認識闘争
∧ ∧ ∧ ∧
∥ ∥ ∥ ∥
採集生産 農業生産 工業生産 意識生産
↑ ↑ ↑ ↑
------物的欠乏------->-類的欠乏->
<共認原理> < 私権原理 ><共認原理>
・人類の社会は、採取生産、農業生産、工業生産、意識生産という大きく4つの生産時代に区分される。
・産業革命以降、工業生産の時代に入ると、土地ではなく機械が生産力の源となる。土地を手に入れるための武力に替わって、機械を備えるための資本力が社会を支配する制覇力となる。つまり、工業生産様式のもとでは、資本に支配される社会=資本主義社会となる。
・1970年代、工業生産の拡大によって、遂にモノの(消費の)飽和限界に行き着き、工業生産に代わって意識生産が社会の生産の主力に成りつつある。
エネルギー消費の面から見ても、‘70年を境に「工業生産から意識生産への生産様式の転換」が起きていることは明らかだといえます。
 [13]
[13]
「金貸しは、国家を相手に金を貸す」 [14]様よりお借りしました
しかし、本来ならば上記のようにモノ(耐久消費財)が全ての家庭にゆきわたって以降は、その転換期(‘70年 貧困の消滅)を境に工業生産(産業部門)は縮小へ向かうはずです(加えて、省エネ技術の開発により同じ生産量におけるエネルギー消費量は少なくなっているはずです)。それが横ばいに留まっているということは、本来は縮小していくはずの工業生産を無理矢理拡大しようとしてきた結果だといえます。
したがって、‘70年以降はエネルギー消費量は、大きくは①本来は縮小すべき生産活動におけるエネルギー消費が横ばいに留まった ②消費活動におけるエネルギー消費の増大 の二つの要因によって拡大し続けてきたといえます。
次回は、②消費活動におけるエネルギー消費の増大について詳しく見ていきたいと思います。