るいネットにこんな記事「くすりは善玉?悪玉?」 [1]がありました。
○○は良薬で××は毒というわけではありません。すべての薬は「毒」にも「くすり」にもなります。
(中略)
くすりとは何なのか、マスコミに惑わされず事実を知りたい。専門家任せにせずもう少し薬のことを知ってくすりと付き合いたいというのが、多くの人に共通する思いではないでしょうか?
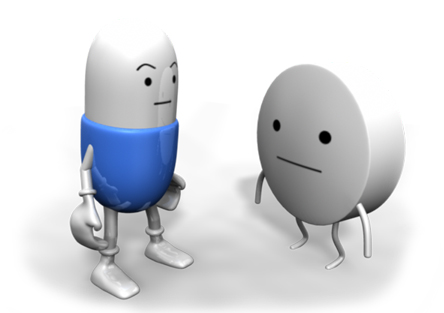
そこで
あまり専門的にならない範囲で、くすりについて調べてみることにしました。
はたして
くすりとは「病気を治すもの」なんでしょうか?
医者はなぜ多種多様のくすりを処方し続けるのでしょうか?
「副作用」のないくすりはできないのでしょうか?
辞書を引いてみると「くすり=化学物質」となっていました。うーむ。
続きはポチッのあとで↓↓↓
「くすり」の世界って学問としてはすごく専門的な領域で、一般人はちょっと立ち入り難いというか、「見ちゃダメ」という不可侵領域のムードすら漂わせている。だからその中身はほとんど知らず(知らされず)、製品になったものだけ医者や薬剤師の言うがまま、あるいはテレビCMにノセられて、日々摂取しています。
日本人はくすり好きなんだそうです。でも、多くの人はくすりについてほとんど知識を持たず、「飲めば治る」と信じて服用しています。私もこれまでくすりって何なのか、考えたことが一度もありません。
生活のなかで当たり前に依存しているけど、もう少しくすりのことを知った上でお世話になったほうがいいんじゃないでしょうかね。
だから
「くすりって何?」
まずはくすりの世界の変遷から見てみます。
太古の昔から人々は自然界にある物質の薬効を発見し、生活に取り入れてきました。
ですが近代医薬の歴史は意外に短くて、1817年に発表された「モルヒネの発見」がその端緒だそうです。
その後の医薬史上の大きな出来事を並べてみると、
1.モルヒネの発見 (1817年発表)
2.合成薬(アスピリン)の開発 (1899年商品化)
3.抗生物質(ペニシリン)の発見 (1928年)
4.ステロイドの登場 (1934年抽出、1948年薬剤利用)
これらの偉業のたびに医療のあり方が変化し、医薬業界は飛躍的発展をしてきた。
【参考:「薬を知りたい-創薬プロジェクトの現場から-」中島祥吉著】
医療の世界でこれらは大事件だったようです。
さて、これら4種の「くすり」はいったいナニモノなのでしょう?
詳細は後稿にご期待ください。