「日本の水資源と水利用の現状 1.列島の水資源」 [1]は興味深い内容でした。ただ、枯渇の危機に反して、日本ではミネラルウォーター市場もどんどん拡大しています(最大ブランドであるサントリー「南アルプスの水」は、一説には年間2200万ケース:2L×6本も売れているとのこと)。水資源とミネラルウォータービジネスの関連について考えてみたいと思います。まずは、下のグラフから。
 [2]
[2]
『H-12 景観の変化から探る世界の水辺環境の長期的トレンドに関する環境社会学的研究』 [3]よりお借りしました。
<1.日本(琵琶湖・淀川水系)>
・急速に水汚染が進んだといわれる琵琶湖も昭和30年代までは、川水、湖水などが浄化せずに直接飲用にされていたことは意外と知られていない。昭和30年代の琵琶湖周辺での洗い場写真などの古写真を活用したディープインタビューにより、人びとの汚染認識は、一般に水質を管理しようとする行政的認識と大きく異なることがわかった。
・行政的水質管理が、水の中の物質の「制御」を狙っているが、人びとが汚いと判断するのは、水や水場との「かかわりが失われること」であるという「関係論的」あるいは「共感論」的認識であった。昭和30年代まで、地域社会では、上水と下水を厳密に分ける「上下水分離システム」が存在し、水場を空間的に使い分けながら、し尿や使い水を肥料として使い回すという仕組みがつくられていた。
・特にし尿について、大便と小便をあらかじめ分離をし、それぞれに肥料として活用する、大小便分離型トイレが有効に機能していた。このような仕組みは個別の家族というよりは地域共同体全体としての共通な水管理の仕組みを作っていた「社会的関係性」の中にうめこまれたといえる。その結果、琵琶湖への汚濁負荷が少なく、琵琶湖の清浄さが確保された。
・しかし、昭和30年代以降の上水道が導入されると、家庭排水が増加し、河川や琵琶湖の汚染がすすんだ。そこで水質汚染対策として行政により下水道システムの導入がはかられたが、その結果上水源も琵琶湖、下水処理水を流す場所も琵琶湖という高度にエネルギーを利用する大循環システムが生まれ、巨額の公共投資を行いながら、水汚染問題の深刻さから解放されていない、という問題をかかえることになった。ここには県や国という中央集権的な行政管理の強化がみてとれる。
この内容からすると、「共同体単位で水管理→中央集権的な水管理(=上水道普及)→生活廃水の増加→水質汚染→下水道の必要性→巨額の公共投資」という流れがあるように思います。つまり、近代的な水道設備の普及が、水使用量の急激な増加、それが水質汚染や水資源の枯渇という問題につながっているのではないでしょうか。なお、これは共同体から核家族への小家族化とも連動しているように思います。では、続きに行く前にご協力よろしくお願いします。
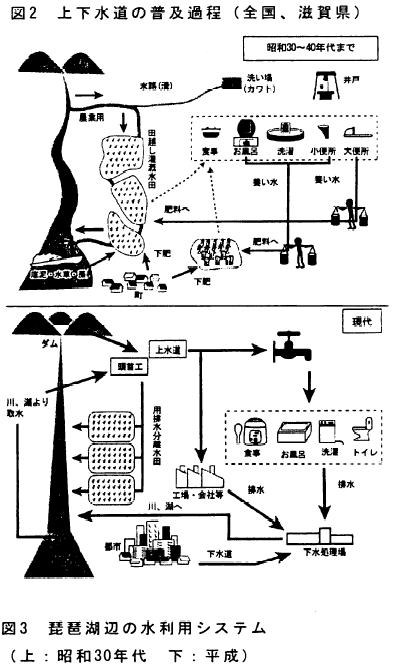 [4]
[4]
村落共同体では水は合理的、衛生的に管理され、環境への負担は非常に小さい。それが、各戸単位での水供給システムである上水道が供給されると、とたんに使用量急増、水質汚染、環境負担増となる。水資源の管理という共通課題がなくなることは地域共同体の必然性を弱めてしまう要因でもあるといえます。庶民(集団)の課題であった「水の管理」を、行政が中央集権的なシステムに組み込んで近代化を図るという構図が見てとれるようです。
19世紀中頃、パリで上水道が普及し始めたとたん、瓶詰めのレマン湖水が売り出されはじめたのは偶然ではないだろう。商業主義の「売る水」思想は、長い管渠に依存する上水システムとセットでもある。
さらに注目されるのが、水道普及にやや遅れる形で「ミネラルウォーター(の原型)」売るということが商売として成立していく事です。自然な水体系と共同体は不可分一体のものでそこには水を売る(市場で取引する)という発想は出てきようが無い。しかし、自然水を浄水処理して管渠で都市に供給する事ではじめて「水道水」という商品になる。ここで、はじめて「水」の市場化の一端が開かれる。つまり、水道水は便利だが、まずいという衛生観念や清潔観念とセットで、より高付加価値な「ミネラルウォーター」が成立する基盤が生まれる。
ミネラルウォーターを売るためには水道普及が必要。ただ、水道水とミネラルウォーターの品質はそれほど違うのかという疑問も湧いてきます。この辺りは、また考えてみたいと思います。ありがとうございました。