前回は、「原子力産業の再編②:BWRとPWRの違いによる力関係は?」 [1]で原発メーカーに関する構図について調べましたが、さらに対象を広くして原子力利権の全体像について見てみたいと思います。
まずは次の資料から見ていきたいと思います。
 [2]
[2]
「エネルギー白書2007年版」より [3]
原子力に関わる利権として、原子炉製造(メーカー)以外に、同時に資源を巡る争奪戦も発生します。世界的な原子力推進の潮流ができ、10年先を見越してウラン資源の高騰もすでに始まっています。
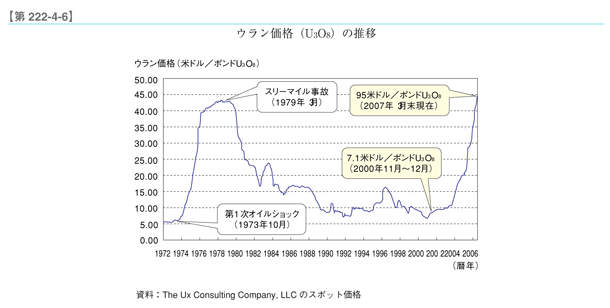 [4]
[4]
さて、続きに行く前にご協力よろしおねがいします。
『温暖化脅威論は原子力利権そのもの』2007/12/04 01:59
何度も何度も書かなくてはならないだろう。
「CO2による地球温暖化脅威論」に込められた恐るべきねらいを。
どっから見てもはっきりしているのは、原子力利権だ。
■原子炉は誰がつくっているか?
・東芝(日本)がウェスティン(米)を買収したグループ、日立製作所(日本)とゼネラル・エレクトリック(米)の連合、三菱重工(日本)とアレバ(仏)の連合、の3グループにほぼ独占されている。(エネルギー白書2007より)
・世界中の原子炉のほとんどは、日・米・仏の会社が作っている。
■燃料のウランは誰が売っているのか
・世界のウラン鉱山は、Cameco(カナダ)、AREVA NC(フランス)、ERA(オーストラリア)等の主要8社で、世界の天然ウラン生産の約8割 (前出白書より)
・さらに、南アフリカの「リオ・チント・チンク」という会社もある。会社と言うよりも、ロスチャイルド財閥系のウラン・シンジケートのようなものらしい。
・原子炉にもウランにも名前の出ているアレバ(仏)は、実はドイツの巨大企業ジーメンスが34%の株を保有している。このジーメンス社の大株主もリオ・チント・チンクだという。 (広瀬隆氏より)
■反米諸国に移る石油利権
田中宇の国際ニュース解説 2007年3月20日
・「セブン・シスターズ」は、エクソン、シェブロン、モービル、ガルフ石油、テキサコというアメリカの5社と、ブリティッシュ・ペトロ-リアムス(BP)、ロイヤル・ダッチ・シェルというイギリス系の2社を指していた。1980-90年代の国際石油業界の再編によって、セブン・シスターズは4社に減った。この4社が世界の「石油利権」を握り「石油はアングロ・サクソン(米英)が支配する」というのが、これまでの常識である。
・新しいセブン・シスターズとは、サウジアラビアのサウジアラムコ、ロシアのガスプロム、中国のCNPC、イランのNIOC、ベネズエラのPDVSA、ブラジルのペトロブラス、マレーシアのペトロナスの7社である。これらは、いずれも所属する国の国営企業である。
・7社は合計で、世界の石油・ガスの産出量の3分の1、埋蔵量の3分の1を握っている。これに対して旧シスターズの4社は、保有油田が枯渇傾向にあるため、今では産出量の1割、埋蔵量の3%しか持っていない。
・だから、石油利権から原子力利権に乗り移ろうとたくらんでいるわけだ。
■ウラン資源を巡る利権
・ウランは足りないのだ。単純に埋蔵量と需要を比較すると、50年ほどで枯渇する。(330万÷6.7万)。危険きわまりない再処理やプルサーマルを行っても、需要が増え続ければ、いつまで保つか?
・10年後にも需給逼迫が懸念され、世界的なウラン獲得競争は更に激化していきます。このような状況を受け、近年、ウラン価格が急騰しています。その一方で、需要の拡大や価格の上昇による投資環境の改善を背景に、世界的な天然ウラン増産に向けた動きも見られます。
(前出白書)
・なんと、7年間で7倍近くに高騰している。原油よりもひどい。この濡れ手に泡のボロもうけに、世界最大のウラン埋蔵国が指をくわえているワケにはいかない、ということで、オーストラリアはめでたく京都議定書を批准した。原発でCO2を減らすことなど、実は当の本人も考えていないだろう。今後、ウランが足りなくなって原発が稼働できなくなるのを見越しているのである。おそらくは、今後オーストラリアでは、ラッド首相率いる国産勢力と、多国籍勢力とのウランをめぐる争いが激化するだろう。
「反戦な家づくり」 [5]さんのブログから引用させていただきました。
これらの情報をもとに、少し整理してみます。
◆石油利権構造の変遷:米英勢力(旧セブン・シスターズ)>反米勢力(新セブン・シスターズ)
↓
◆「地球温暖化脅威論」のプロパガンダ:マスコミによる共認形成(支配)
↓
◆CO2削減の世界共認:京都議定書の締結
↓
◆原子力発電推進の共認形成:温暖化と石油資源枯渇が前提条件
↓
◆新市場の形成と拡大:その成長に乗じた投資市場
①原子炉の建設市場
②ウラン資源市場
③CO2排出権の売買市場
というように新たな市場がいくつも生み出され、金融資本家がその新たな利権構造を目当てに投資していく。つまり、「地球温暖化問題」とは、実はあくまでも旧利権から新利権へと乗り換えていくためのストーリーであると見ることができると思います。そういった背景も踏まえて、環境問題を見ていく必要があるのだと思います。