

トリハロメタンという物質の名前を聞いた事がありませんか?
水道水汚染の話では、とりわけ恐れられている物質で、この名前を出せば、浄水器が飛ぶように売れるらしい。浄水器のセールストークには必ず入っています。
まずトリハロメタンの毒性  が一躍有名になった経緯を確認してみましょう。
が一躍有名になった経緯を確認してみましょう。
トリハロメタンが登場したのは、
1972(昭和47)年のオランダ。ロッテルダム水道のルーク博士はライン河の河川水からトリハロメタンの一種であるクロロホルムを検出し、それが原水には含まれず、河川水を塩素処理することによって生成されたものだということを初めて報告し、注目された。
また1974(昭和49)年にはハリス博士が、米国ミッシシッピ州ルイジアナの住民のがん発生率が高いのは、水道水中に存在している有機物が関係していると報告。これ以来、世界各地で水道水の安全性について再検討が精力的に行われるようになった。1975年米国の環境保護庁は全米113都市の水道水中の有機物について広範な調査を実施し、トリハロメタンが多くの水道で検出されることを明らかにした。
これによって、トリハロメタンが非常に危険な物質  となったのです。
となったのです。
さて 😈 不安感  を煽ったところで、ちょっと一服して応援をポチッとお願いします
を煽ったところで、ちょっと一服して応援をポチッとお願いします 
ポチッとありがとうございました 
水道水に含まれるトリハロメタンのうち60~90%がクロロホルムです。
確かにクロロホルムといえば、中学や高校の理科の解剖実験等で麻酔として使ったことのある人も多いと思うので、その毒性は想像しやすいと思います。日本では毒物及び劇物取締法の医薬用外劇物に指定、労働安全衛生法の第一種有機溶剤に指定されています。
但しその発がん性については、IARC(国際がん研究機関)の見解ではトリハロメタンが人に発がん作用を示す確証はない。
それでも各国はクロロホルムがヒトに発がん性を示すと仮定し、一生涯その水を飲み続けても発がん率が10万分の1を超さないレベルで水質基準を設定していて、WHO(世界保健機構)では「0.2mg/L」に設定している。日本の水質基準は「0.06mg/L」となっている。
日本の水質基準がWHOをより厳しい要因は、恵まれた水源の存在にある。日本は汚染度の低い上流部から取水し、主に下水を海に流すシステムを取っている。
それに比べて欧米の河川は長大で、日本のようなシステムを取れない河川が多い。ライン川は最たるもので河口にあるオランダはいわば上流にある各国の排出した下水道水を水源にすることになり、汚染度は日本人の想像を絶する。
水質基準は各国の事情を加味した現実的な数値となっている。日本は世界基準から見てもきれいな水を飲んでいることになる。
ではクロロホルムの毒性について最も代表的なLD50(半数致死量:ラットの半数が死んでしまう量)で比較したサイト(狸の水呑み場 [1])があったので、それを参考にしてみましょう。
・タバコのニコチン LD50 50mg/kg
・お茶のカフェイン LD50 200mg/kg
・水道のクロロホルム LD50 900~2000mg/kg
・食塩 LD50 4500mg/kg
これをやや強引ですが、体重70kgの成人に換算してみると
・ニコチン 半数致死量 3.5g 摂取量:ライト(0.3mg)を20本吸って6mg
一日摂取量は半数致死量の1/580
・カフェイン 半数致死量 14g 摂取量:紅茶1杯(200mg)で100mg
一日摂取量は半数致死量の1/140
・クロロホルム 半数致死量 63g 摂取量:ジョッキ大を4杯(2L)で0.12mg
一日摂取量は半数致死量の1/525000
・食塩 半数致死量315g 摂取量:ポテトチップス(85g)を1袋で0.9g
一日の摂取量は半数致死量の1/350
水道水に含まれるクロロホルムのリスクが、タバコやお茶などに比べるといかに小さいかが解ります。
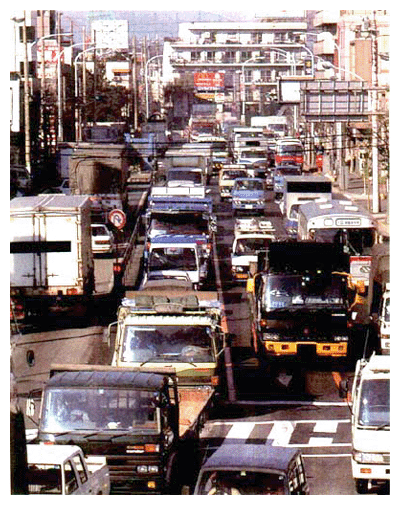
体内に蓄積されるのでは?という疑問もありますが、例えばクロロホルムは腸管から吸収されて血液中に移り、70~80%が肺から呼気に出るし、代謝されたクロロホルムも最後は二酸化炭素になって排泄されるので、蓄積しやすいことはなさそうです。
「水道水ががんを増やしている。」というハリス博士の報告によって、トリハロメタンは多くの人々の関心を集めたが、実は同じ報告書の中には
「洗濯や炊事など、頻繁に水道水を使う婦人層にはむしろがんの発生率が低いという矛盾がある。」という一節もあり、根拠のない怪しげな情報に振り回されたダイオキシン騒動と同様の構造ではないかと思われる。
元々市場拡大による環境問題の対策としての答えが、新たな商品開発(=市場拡大)になっている場合は、その根拠から検証が必要と思われます。
※ちなみにWHOはトリハロメタン類の20%を飲み水から摂取すると見込んで水質基準を決めている。つまり80%は飲み水以外の空気(排気ガスが中心)や食物から摂取するという前提です。
【参考文献:「水と健康」林俊郎 日本評論社】