京都議定書に基づく温暖化対策は現状どこまで実現されているのか?
日本の現状について調べてみました。
議定書では、日本の温室効果ガス削減目標として、1990年比、6%削減が義務付けされましたが、現状では、下図のように総排出量は減るどころか増え続けている。
これを見ると、目標は本当に実現可能なのか?不可能に近いのではないか、と思えるような現状である。これだけ温暖化対策が騒がれていながら、効果が出ていないのは何でだろう?

図はhttp://www.glass-fiber.net/kankyo/kankyo2.html [1]より引用
この先、読みたいって思った方はポチッとお願います!
先ず、京都議定書に基づくCO2削減負担は、各国間で異なる。
日本は90年比6%削減となっているが(欧は8%、米は7%)、主要先進国の中で最もエネルギー効率がよく、1CO2トン減らすのに、欧米の1.3~2倍のコストが必要だと言われており、この削減目標はかなり厳しい数値である。
また、エネルギー消費量をGDPで割った指標で比べても、日本はアメリカの1/3、ドイツの60%しか使っていない ので、かなり省エネ化が進んでいる状態である。(下図参照)
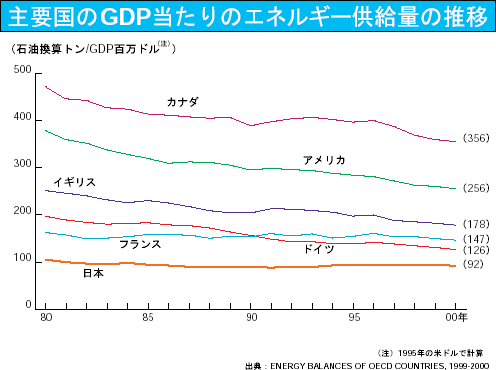
図は
これは、70年代に2度のオイルショックを経験し、大きな経済的打撃を受けると共に、省エネルギーの重要性が一般市民の意識にも浸透し、法整備や各種省エネルギー政策の推進などが進められた結果と言える。つまり、日本が経済成長を維持しながら他の欧米諸国と同様に省エネルギー化のスピードを維持すること自体が大変難しくなってきている、ということです。
では何が問題か?、分野別のCO2排出構造はどうなっているのでしょうか?
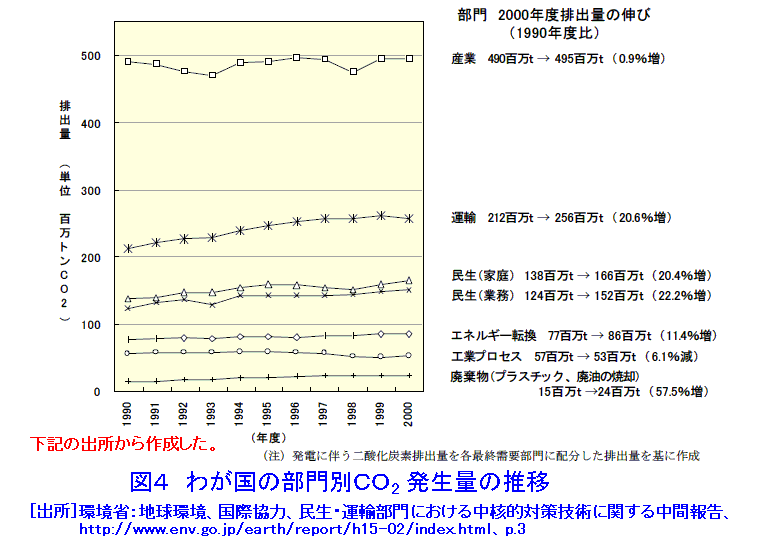
http://atomica.nucpal.gr.jp/atomica/pict/01/01080207/05.gif [2]より引用
伸びが多いのは、
民生部門の業務、つまりオフィス、店舗、官庁や学校などの公的部門も含んだもので、2000年度で90年比、+22.2%増加
民生部門の家庭は、同+20.4%増加で、冷暖房、家電、ゴミ処理がその主な排出源です。
運輸部門は、同+20.6%増加で、旅客、自動車
最も排出削減に貢献しているのは、産業部門で同+0.9%、という結果です。
民生部門が多いのは、1990年代にエネルギー価格が下落し続ける中で、家電の大型化、高機能化、IT化の進展により消費が急増した為と考えられます。
しかし、「京都議定書は実現できるのか」平凡社 石井孝明著 では次のような要因についても述べています。
>生協が電力と都市ガスの使用量を2001年までの4年間、全国300世帯の組合員を対象に調べたところ、家族構成の変化でエネルギー消費が増えている可能性が大だと言う。
>単身世帯の電力使用量は4人世帯の一人当たりの使用量のガスで3倍、電気で1.8倍である。また、90~00年に全世帯数の伸びが14%だったのに対し、単身世帯の伸びが37%で、実は、共同生活世帯が減ったことがその最も大きい要因ではないか、ということです。
さらに、消費の伸びが大きいのが運輸部門の自動車であり、’90~’00年の自動車保有台数の伸びは30%に対し、乗用車台数の伸びはなんと56%です。
この中でも、企業が運用している輸送機関については概ね減少傾向と、かなり頑張っている。
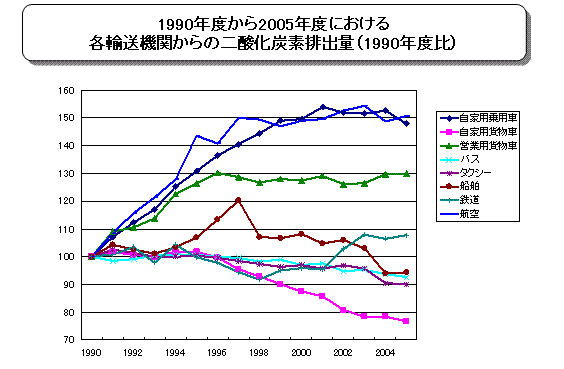
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyou/ondanka1.htm#genjou [3]より引用
つまり、温暖化対策は、産業界に厳しく、消費者には甘すぎるのではないか!と言いたくなりますが、皆さん、どうでしょうか?
これら温暖化対策の難しさについて、元資源エネルギー庁長官の稲川康弘氏は次のように述べています。
>「第一次オイルショックから現在を比べると、国民のエネルギー消費量は約3倍になります。行政側では京都議定書など日本のエネルギー政策の転換ごとに、強めの規制手段をいろいろ考えました。エネルギー税の増額、計画配電、エネルギー利用規制などですが、どれも断念しました。過剰な規制をすることは統制経済になり、日本の現在の社会制度と矛盾します。国民がそれを認めるとは思えませんでした。今でもそうでしょう」
この言葉からは、さらなる温暖化対策の手段としては、聖域である家庭=個人消費に手をつけなければ解決しないこと、さらに、そこにあるのは経済成長という政策目標よりも、もっと根っこにある絶対的な壁=「個人の自由を侵してはいけない」が最大のネックだと政策担当者自身も感じているのではないでしょうか!