こんばんは、 かっし~です 
前回、10月23日にアップした中国の砂漠化の土台は、四大文明まで遡る?! [1]では、流出型農業(=西洋型農業)と回収型農業(=東洋型農業)という、古代からの農業形態の違いが地力を左右し、そして地力▼が砂漠化の根底にあるお話をしました 😀
今まで、砂漠化問題⇒植林  したらいいじゃん!!と超短絡的に考えていた…
したらいいじゃん!!と超短絡的に考えていた… 
今後は、地力△から様々な問題を考えてみようと思います 
そして今回は、いきなりですが・・・
 この人
この人 
 は何をする人でしょうか
は何をする人でしょうか  (ちなみに右の写真はこの人が担いでいるものです
(ちなみに右の写真はこの人が担いでいるものです  )
)
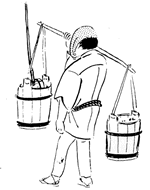

答えに行く前に、ポチっとお願いします 
10月23日の記事では、日本も回収型農業であることをちらっと書きました  ということは、日本も人糞を肥料に使っていたということ
ということは、日本も人糞を肥料に使っていたということ  人糞肥料は下肥と呼ばれ、一説ではその歴史は非常に古いようです
人糞肥料は下肥と呼ばれ、一説ではその歴史は非常に古いようです 
お隣中国は漢王朝の時代(紀元前202年~紀元8年)、既に人糞を肥料の1つとして使用していたことが書物に書かれています  そして、その書物は、平安時代に日本に伝わっているとされています
そして、その書物は、平安時代に日本に伝わっているとされています 
また、それ以前にも渡来人などによって、中国から様々な農業技術が伝えられており、それによって人糞を肥料として利用することも伝えられていたのではないかとのことです ![]() (参考 [2])
(参考 [2])
※漢王朝は、中国南部長江流域を主とした王朝。まさに前回の長江文明(=回収型農業)が栄えた地域です
また、江戸時代には、人糞回収において、都市  農村のシステムとして確立していました
農村のシステムとして確立していました 
以下、大江戸リサイクル事情 [3]より引用
米は備蓄分と種籾分を残して食糧にまわっていきました。食糧として人間のお腹に入り、体内にエネルギーとして吸収された後は排泄されます。この排泄物が江戸時代のもっとも重要な肥料でした。特別な設備もエネルギーも不要、ただ集めるだけでチッソやリンを豊富に含んだ有機肥料を入手できたのです。
この下肥を農家の人がお金を払ったり、野菜などの現物と交換する形で買い取りました。農家では江戸の特定の地域や家と契約を結んでいて、定期的に訪問して買い取っていたのです。江戸の町の住人は下肥の生産者であり、農家の人は下肥の消費者、そして農家の人は野菜など農作物の生産者となり、町の人はその消費者となる、このようなリサイクルシステムが、江戸では自然に成立していたのです。
上の絵の人は、都市から農村へ下肥を運ぶ人だったんですね ![]()
当時、下肥は金肥  とも呼ばれ、大変重宝がられていました
とも呼ばれ、大変重宝がられていました
では、日本で、人糞肥料が用いられていたのは、江戸時代にまで遡るのかというと、これが意外と近年まで使われていたんです ![]()
皆さん、『肥溜め』ってご存知ですか  私は、20代で田舎育ちですが、さすがに本物を見たことはないんですが、少し上の年齢の方だと、「小さい頃、肥溜めにはまって・・・
私は、20代で田舎育ちですが、さすがに本物を見たことはないんですが、少し上の年齢の方だと、「小さい頃、肥溜めにはまって・・・  」なんて話もめずらしくない
」なんて話もめずらしくない  会社の40代の先輩は、小さい頃、日常にあったそうです
会社の40代の先輩は、小さい頃、日常にあったそうです 
この肥溜めこそが、人糞肥料そのもの!!人糞は、そのまま畑に撒くと作物を傷めてしまうので、一旦、発酵させる必要がありました。その、場所が『肥溜め』だったんです 
江戸時代以降も終戦まで、この回収システムは盛んに行われていましたが、戦後、GHQから衛生上の問題ということで禁止されたようです 😥 しかし、実際は、地方では行われていたということなのでしょう 
40代の先輩が小さい頃というのだから、今から30年ほど前・・・1970年頃・・・といえば、日本では高度経済成長が終焉し、貧困がなくなった頃。 ![]()
う~ん、戦後のアメリカ支配と、貧困の消滅。このあたりに、日本から人糞肥料が使われなくなった原因がありそう 